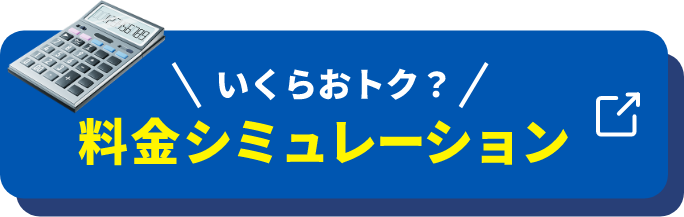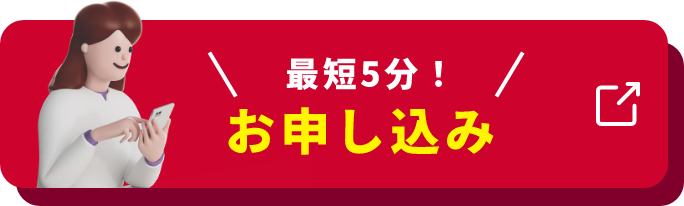EVとPHVの違いとは?仕組みやコストを比較しながら徹底解説

昨今、環境への配慮と燃料費の節約を両立できる点で、EV(電気自動車)やPHV(プラグインハイブリッド自動車)などの電気自動車への関心が高まっています。どちらも電気で走行できる点で共通していますが、その仕組みには違いがあります。
本記事では、EVとPHVの基本的な仕組みや違い、それぞれのメリット・デメリット、維持費を分かりやすく解説します。自分のライフスタイルに合った電気自動車選びの参考にしてください。
EV・PHVとは?違いを解説
EVとPHVは、どちらも従来のガソリン車よりCO₂排出量を大幅に削減できることが特徴ですが、仕組みや使い勝手は異なります。
ここでは、EVとPHVの特徴や違いについて詳しく解説します。
EV(電気自動車)とは
EV(Electric Vehicle/電気自動車)とは、ガソリンなどの化石燃料を一切使わず、電気のみで走行する車です。エンジンの代わりにモーターを搭載し、大容量バッテリーに蓄えた電力で駆動します。そのため、走行中のCO₂排出がゼロであり、環境にやさしい点が最大の特徴です。
充電は家庭用のコンセントや急速充電スタンドで行うことが可能で、維持費もガソリン車と比較して低く抑えられる傾向があります。ただし、長距離を移動する際は、充電スポットを事前に確認し、こまめな充電計画を立て、早めに充電施設へ立ち寄る必要があります。
PHV(プラグインハイブリッド自動車)とは
PHV(Plug-in Hybrid Vehicle/プラグインハイブリッド自動車)は、電気とガソリンの両方を動力源として利用できる車です。
モーターとエンジンの両方を搭載しており、電力が十分にある間はモーターのみで静かに走行するため、主に近距離の通勤や買い物などに便利です。また、電力が不足すると自動的にエンジン走行に切り替わるため、長距離でも安心して走行を続けられます。
自宅での充電が可能である点はEVと同様ですが、PHVはガソリンを併用できることで航続距離に不安がなく、充電スポットが十分にない場所でも安心できることが大きな強みです。
PHVは、EVのエコ性能とガソリン車の利便性の両立させた「いいとこ取り」の車種といえるでしょう。なお、自動車メーカーによっては、「PHV」や「PHEV」と表記されることもありますが、基本的な仕組みは同じです。
EV・PHVの違い
EVとPHVの違いを理解するためには、HV(ハイブリッド自動車)も含めて考えると分かりやすくなります。
HVは、エンジンを主動力としながらモーターを補助的に使用する構造で、外部充電が不要な自動車です。
PHVは、HVに外部充電機能を加えたタイプです。短距離であれば電気のみで走行可能で、電力が不足するとエンジンに自動的に切り替わるため、長距離でも安心して利用できます。
EVはさらに異なり、厳密には「BEV(Battery Electric Vehicle)」と呼ばれ、ガソリンタンクを持たず、バッテリーに貯めた電力とモーターのみで走行します。CO₂排出ゼロの環境性能が特徴ですが、バッテリー残量に注意が必要です。
HV、EV、PHVの特徴の違いは、下表の通りです。
| 特徴の違い | EV | PHV | HV |
|---|---|---|---|
| ガソリンタンク | × | 〇 | 〇 |
| バッテリーの電力で走行 | 〇 | 〇 | × |
| 外部充電 | 〇 | 〇 | × |
| エンジンとモーターで走行 | × | 〇 | 〇 |
| 走行中の充電 | × | 〇 | 〇 |
PHVはEV(BEV)に比べてエンジンとモーターを併用することで、効率的に走行できるという特徴があります。用途やライフスタイルに応じて、最適な車種を選ぶことが重要です。
EV・PHVのメリット・デメリットを比較
EVとPHVはどちらも環境に優しい次世代の車として注目されていますが、それぞれに異なる特徴と利点・課題があります。
ここでは、EVとPHVのメリットとデメリットを比較し、利用シーンやライフスタイルに合わせた選び方の参考になるよう詳しく解説していきます。
| EV | PHV | |
|---|---|---|
| メリット | ・二酸化炭素を排出しない ・振動や走行音が静か ・ランニングコストが安い ・非常電源として利用できる ・国や自治体の補助金、税制優遇を受けやすい |
・近距離ならEVと同様に電気のみで走行できる ・ガソリン走行に切り替えられ、長距離も安心 ・外部充電と給油の両方が可能で、利便性が高い ・非常電源として利用できる |
| デメリット | ・航続距離がガソリン車に比べて短い ・車両価格が高め ・充電場所が少ない ・充電に時間がかかる |
・車両価格やメンテナンス費用が高め ・バッテリー容量はEVより少なく、電気走行距離が短い |
EVのメリット・デメリット
100%電気で走行するEVは、ガソリン給油やオイル交換の必要がないため、ランニングコストを抑えられるというメリットがあります。電気による走行は二酸化炭素を排出しないため、環境にも優しく走行中の振動や音も気になりにくいです。
国や自治体による補助金やエコカー減税などの税制優遇も充実しており、導入時の負担を軽減する制度も整備されています。さらに、EVはバッテリーに蓄えた電力を外部電源として利用できるため、非常時の蓄電池代わりとして活用できる点もメリットです。
一方で、EVは遠距離を走行する場合はバッテリーの充電切れに注意しておかなければいけません。事前に、目的地や経路上に充電施設があるか確認しておくと良いでしょう。
また、ランニングコストは安いものの、バッテリーが高価なことから、車両価格は一般的にガソリン車よりは高めです。加えて、公共の充電インフラがまだ十分に整っていない地域もあり、特に自宅で充電できない場合は充電設備に行き、充電を待つ必要があるため、急ぎの移動が必要な場面ではデメリットとなり得ます。
PHVのメリット・デメリット
電気走行とガソリン走行が可能なPHVは、バッテリーの充電が少なくなってもガソリンで走行できるため、遠距離のドライブでもガソリンスタンドさえあれば安心です。日常の通勤や買い物などであれば、充電さえしておけばガソリンを使わずに走行できます。さらに、PHVも充電した電気は蓄電池として活用できるため、停電時やアウトドアでも活躍するのもメリットです。
一方で、PHVは大容量のバッテリーやハイブリッド自動車のモーターを搭載しているため、一般的なガソリン車やハイブリッド車と比べて車体価格は高めで、EVと同等または場合によってはやや低い価格帯になっています。また、バッテリー容量はEVよりも小さく、電気のみで走行できる距離には限りがあります。日常的に電動走行のメリットを十分に活かすには、こまめな充電が必要になる点も考慮すべきポイントです。
EV・PHVのトータルコストを比較
EVとPHVを比較する際には、車両価格やメンテナンス費用だけでなく、日々の使用で発生する電気代やガソリン代も含めたトータルコストが判断材料になります。どちらが自分にとって経済的かを把握するには、以下のコストを踏まえて比較することが大切です。
- 電気代・ガソリン代
- 車両代・メンテナンス費用
- 補助金・税金などの制度
ここでは、具体的な車種のデータをもとに、EVとPHVの燃料コストの違いについて詳しく見ていきましょう。
電気代・ガソリン代
EVの電気代とPHVのガソリン代を比較する際は、以下の3つのポイントを確認しておくと、実際のランニングコストが分かりやすくなります。
- バッテリーの容量
- ガソリンの単価
- 航続距離(WLTC)
代表的な車種を例に具体的な試算をしてみましょう。
EVの例として日産のリーフXの電気代を試算すると、以下のようになります。
| ・バッテリー容量:40kWh ・航続距離:約322km(満充電時) ・電気代:単価を31円/kWhとした場合、フル充電にかかる費用は31円×40kWh=1,240円となる →1,240円の電気代で約322km走行できる(1kmあたりのコスト: 約3.85円) |
次に、PHVの例としてトヨタのプリウスPHVを見てみましょう。なお、PHVは電気で走る場合(EVモード)とガソリンで走る場合(ハイブリッドモード)で計算が異なるため、それぞれのモードの電気代・ガソリン代を試算しました。
|
【電気で走る場合(EVモード)】 【ガソリンで走る場合(ハイブリッドモード)】 |
このように1kmあたりのコストを比較してみると、わずかにEVの方が経済的です。
PHVはガソリンの単価が大きく影響します。ガソリンが安い時期であれば、燃料代をさらに抑えられる可能性が高いでしょう。
なお、EV・PHVともにガソリン車との比較では安価であり、燃料代の面で経済的な選択と言えます。
電気自動車の充電料金は?お得に充電する方法やガソリン代との比較
車両代・メンテナンス費用
EVやPHVを購入する際に最も大きな負担となるのが、車体価格です。一般的に、いずれもガソリン車と比べて車両代が高額になる傾向があります。
その背景には、主にバッテリーコストの影響があります。EVの場合、走行に使用する電力を蓄えるリチウムイオン式バッテリーが高価で、これが車体価格を押し上げる大きな要因となっています。
PHVは、リチウムイオン電池やニッケル水素電池を採用した駆動用のメインバッテリーが搭載されており、電動走行を支えています。さらに、ハイブリットシステムに電力を供給するための補助に補機バッテリーも必要となるため、ガソリン車よりもコストがかかります。
車体価格は以下のように高額となりやすいです。
- 日産 リーフ(EV):408.1万~561.6万円
- トヨタ プリウスPHV:390.0万~460.0万円
- 三菱 アウトランダーPHEV:526.3万~659.4万円
これらの車体価格はグレードやオプション装備によって異なり、さらに高額になるケースも多く見られます。
なお、EVやPHVは購入後に気になるポイントが、駆動用バッテリーの劣化です。
例えば、日産リーフには新車登録から8年間または走行距離16万kmまでのどちらか早い方に達するまでバッテリーの保証がついていますが、それを超えた後にバッテリーを交換する場合、バッテリー本体と工賃により、50万円以上の費用がかかるケースがあります。バッテリーが著しく劣化した場合、買い替えを検討する人も少なくありません。
EVやPHVを選ぶ際は、バッテリーの保証期間や寿命をよく確認し、できるだけバッテリーに負荷をかけない使い方を心掛けておくことが大切です。
補助金・税金などの制度
国や自治体では、EVやPHVなどの電気自動車を広く普及させるため、購入費用に対して、さまざまな補助金や助成金、税制特例措置を実施しています。
具体的に、国が令和7年度に実施している補助金制度では、車種ごとに設定された金額が支給され、最大で90万円の補助金を受け取ることができます。
また、自治体ごとに独自の助成制度も用意されており、EVやPHV(PHEV)に対する助成金を、国の補助金に上乗せして支払われる仕組みです。
さらに、EVやPHVを購入すると税制特例措置として、以下のような免税・減税が受けられます。
- 環境性能割:非課税
- 自動車重量税:エコカー減税で免税
- 自動車税:グリーン化特例で減税
税制特例措置は都道府県によって異なるため、各自治体のホームページ等で確認してみると良いでしょう。車体購入に対する補助金・助成金の活用と税制特典を受けることで、よりおトクにEVやPHVを導入・維持できるようになります。
EV・PHVに関するよくある質問
ここまで、EVとPHVの違いを紹介しました。しかし、まだ不安や疑問が残り、どちらを購入すべきか悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。ここでは、EV・PHVに関するよくある質問をまとめました。
FCV・HVとの違いは?
EVやPHVとよく比較される車種に、FCV(燃料電池自動車)とHV(ハイブリッド自動車)がありますが、それぞれ使用する燃料や仕組みに大きな違いがあります。
- FCV:水素で自家発電した電気を使用する
- HV:ガソリンと電気の2つを使用する
FCV(Fuel Cell Vehicle)は、水素を燃料に使用します。水素と酸素との化学反応によって電力を作り出し、その動力でモーターを動かして走行する仕組みです。二酸化炭素を排出せず、クリーンな走行が可能ですが、水素ステーションの整備がまだ十分でないため、対応車種や利用できる地域が限られています。
一方、HV(Hybrid Vehicle)はガソリンを使うエンジンと、走行しながら充電できるモーターを使い分けながら走行し、燃費向上を目指すハイブリッド自動車です。HVはすでに多くの自動車メーカーから販売されており、モデルも豊富に揃っています。
EV・PHVのどちらを選べばいい?
EVやPHVはどちらも環境性能や走り心地に優れた車種ですが、生活スタイルによって最適な選択は異なります。
EVとPHVで悩んだ場合は、以下のポイントを参考にしてみてください。
| おすすめの人 | |
|---|---|
| EV | ・毎日の走行距離が短めの人 ・自宅に充電設備を設置できるまたは行動範囲内に充電スポットがある人 ・メンテナンス費用を減らしたい人 |
| PHV | ・長距離移動が多い人 ・充電環境が整っていない人 ・「いざというときはガソリンも使える安心感」が欲しい人 |
長距離を走行する機会の多い方の場合、EVではバッテリーの容量が不足した場合、途中で充電スポットを探す必要があります。一方で、街乗り中心で買い物の合間に充電できる方であれば、待ち時間も有効に使えるためEVが適しているでしょう。
EVの充電量による航続距離に不安がある方には、ガソリンを使いつつ電力で走行できるPHVがおすすめです。ガソリンの消費量も減り、ランニングコストの削減にもつながるでしょう。
EVとPHVで悩んだ際は、日々の運転距離や使用頻度などをもとに検討すると選びやすくなります。
EV・PHVでコストを抑える方法はある?
EVやPHVを利用する際、日々の運転や充電の工夫によって、電気代や給油費用を抑えることが可能です。まず、急ブレーキや急加速を避けて丁寧に運転することで、電費や燃費が向上し、消費するエネルギー量を抑えられます。これにより、電気代や給油費用の節約が可能です。
また、EVやPHVは可能な限り充電での走行を中心に活用すると経済的です。特にPHVは、ガソリンよりも電気で走行する方がコストを抑えやすいため、日常の通勤や買い物などは充電走行を優先するのがおすすめです。
さらに、充電する時間帯や場所を工夫することで、維持費をさらに抑えられます。特に、以下のポイントを意識すると良いでしょう。
- 外出先の無料充電スポットを活用する
- 自宅での充電は電気料金が安い時間帯に行う
EVやPHVは、公共施設やショッピングセンター、ディーラーなどでの充電が無料となる場合があります。また、自宅でEVやPHVを充電する際は、深夜など電気料金の安い時間帯に行うことがコストダウンにつながります。加えて、自宅の電気料金プランを確認し、おトクな充電ができるプランを見つけることもおすすめです。
EV・PHVの費用をおトクにするならidemitsuでんき
EVやPHVは、バッテリーに充電した電気を使って走行できる車です。EVは電力のみ、PHVは電力とガソリンを併用して走行します。
ガソリン価格の高騰が続いており、燃料費の悩みの種となっている方も多い中、EVやPHVは燃料費の節約に大きく貢献します。
さらに、EVやPHVを所有している方や購入を検討している方々は、電気代の見直しによって、車のランニングコストと電気代の負担を同時に軽減できる可能性があります。
そこでおすすめなのが、idemitsuでんきのクルマ特割「EVコース」です。このプランでは、電気料金から毎月200円引きとなるEVユーザー限定の特典に加え、「EV充電タイム」が設定されており、EVやPHVを指定の時間に充電するだけでポイントが貯まる特典があります。還元されるポイントは、楽天ポイント・dポイント・Pontaポイントの中から選べるため、日々のお買い物にも役立つでしょう。
また、オール電化住宅向けに、オール電化向けプランのご用意もありますので、夜間の電力単価が安価な時間帯に充電をすることもできます。
電気代が高騰している今だからこそ、電気自動車の充電コストを抑えながらポイントも獲得できるidemitsuでんきへ切り替えることで、多くのメリットが期待できます。EVやPHVをより経済的に利用したい方は、ぜひ検討してみてください。