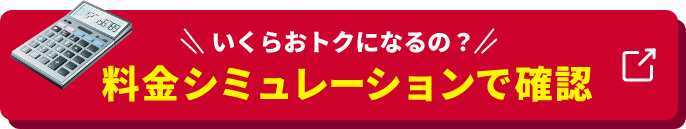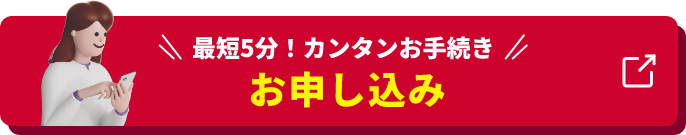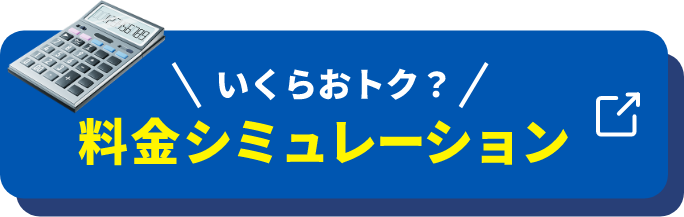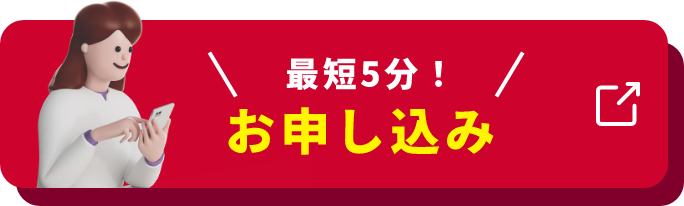電気代が高い理由は?原因の調べ方や対処法を紹介
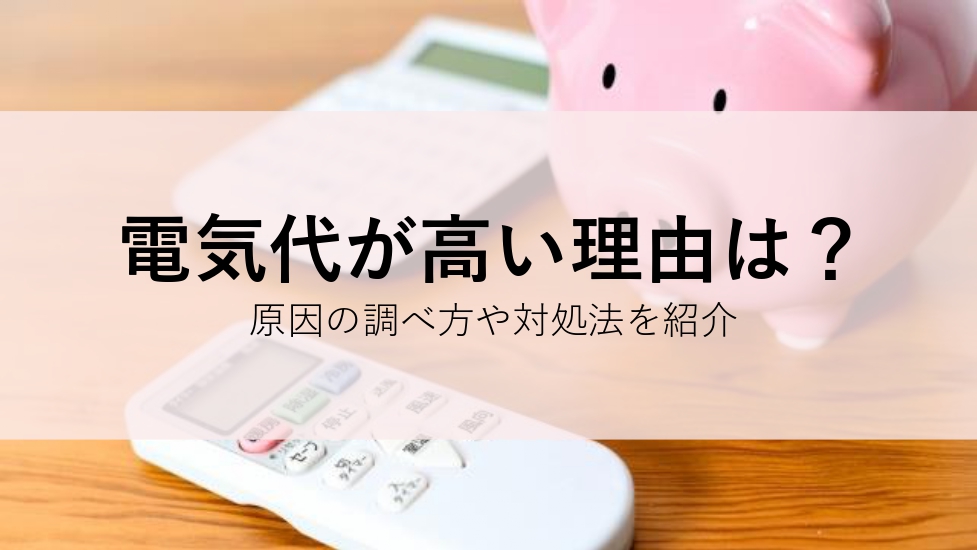
「最近電気代が高くなった」と感じている方は多いのではないでしょうか。電気代が高いと感じたら、まずは原因を確認し、適切な対策を講じることが大切です。
本記事では、電気代が高くなる原因や、電気代を抑えるための方法について詳しく解説します。また、世帯規模ごとの電気代の平均額やおトクな電力会社もご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
電気代が高すぎる?考えられる原因
電気代が高くなる原因にはいくつかの要素が関わっており、主な原因として以下が挙げられます。
- 電気の使用量が増えた
- 消費電力が多い家電や古い家電を使っている
- ライフスタイル・使用時間が変わった
- 契約しているプランがライフスタイルに合っていない
- 漏電している
- 発電量の燃料費が上がっている
- 市場連動型のプランで市場価格が高騰している
ここでは、各要因について詳しく解説していきます。
電気の使用量が増えた
電気の使用量が増えると、その分電気代は高くなります。特に夏場のクーラーや冬場の暖房器具の使用時間が長くなると、電気代が大幅に増加しやすくなります。
電気代が気になる場合、最近新しく導入した家電や、使う頻度が増えた家電がないか振り返ってみましょう。
消費電力が多い家電や古い家電を使っている
夏場や冬場のエアコンは消費電力が多く、その使い方が電気代に大きく影響します。また、エアコンに加え、冷蔵庫や、テレビ、照明器具など、一年を通して使う時間の長い家電の電気代が古い場合は商品電力が多く、電気代が高止まりしやすくなります。
例えば、10年前の家電と比べると、最新の製品は以下のように消費電力が大幅に改善されています。
- 電気冷蔵庫:35%減
- エアコン:15%減
- テレビ:31%減
- 照明器具:86%減
古い家電を使い続けている場合、買い替えを検討することで電気代の削減につながるでしょう。
ライフスタイル・使用時間が変わった
同居人が増えたり在宅ワークが増えたりと、ライフスタイルの変化で電気の使用量が増えると、電気代が高くなります。また、深夜の電気代が安いプランに加入したまま、日中に電気を使うことが多くなれば、電気代が割高になってしまっている可能性があります。
必要のない家電をこまめにオフにする、省エネモードを活用するなど節電を心がけましょう。また、料金プランに合わせて夜間や早朝の電力料金が安い時間帯を狙って家電を使うのも一案です。
契約しているプランがライフスタイルに合っていない
電気料金は、ライフスタイルに合わせていくつかのプランが用意されていることが多いです。例えば、家族3人で暮らしているのに1人暮らしにメリットの大きいプランを契約しているなど、ライフスタイルとプランが合っていない可能性も考えられます。
夜間に多くの電力を使用する場合は、夜間の電力料金が安く設定されているプランに変更するなど、家族形態やライフスタイルにあったプランへの変更を検討しましょう。
電気市場価格が高騰している
電気代が高くなるもう一つの大きな要因として、電気の市場価格の高騰があります。電気の市場価格は30分毎に変動し、その価格変動が電気代に反映される場合もあります。
電気市場価格が高騰する要因には、電力需要の増加や燃料の在庫不足などが挙げられます。特に、2020年から2022年にかけては、大寒波や液化天然ガス(LNG)不足によって市場価格が一時的に200円/kWhを超える高値を記録しました。以降、電力会社が料金を引き上げており、家計への負担が大きくなっています。
漏電している
コンセントやプラグの劣化、家電内部の故障などが原因で漏電が発生すると、通常はブレーカーが落ちて電気が遮断されます。しかし、ブレーカーが正常に動作しない場合、電気が流れ続けることになり、常に電気を使用している状態になるため、電気代も高くなります。
漏電すると感電や火災などのリスクも高まりますので、漏電が疑われる場合は、家電やコンセントに異常がないか確認し、早急に対応しましょう。
発電量の燃料費が上がっている
電気料金の計算方法には、大きく以下の2つのタイプがあります。
- 固定単価プラン
- 市場連動型プラン
固定単価プランは決まった料金単価で電気料金を計算したうえで、発電に使われる原油・石炭・液化天然ガスの輸入価格の変動を「燃料費調整額」として加算または減算することが一般的です。輸入価格が上昇傾向にあるときは燃料費調整額も上昇しやすく、電気料金も上がります。
ただし、燃料費調整額の計算における輸入価格は、一般的には数カ月前の価格を、3か月程度平均するため、急激に輸入価格が上昇した場合でも燃料費調整額の上昇は緩やかで、今後の電気代の変動を見通すこともできます。
市場連動型のプランで市場価格が高騰契約している
もう片方の市場連動型プランは、電気の市場価格に応じて毎月あるいは毎時間の料金単価が変動するプランです。電気の市場価格は主に電気の需要と供給のバランスによって決まるので、発電量や季節的な需要の高まりのほか、天候などの影響も受けます。安価に推移することもある一方で、価格が高騰したり高値で推移したりすると、電気代が上がる要因となります。ます。燃料費調整額と比較して、電気代の変動を見通しづらいことも特徴です。
特に、2020年から2022年にかけては、大寒波や液化天然ガス(LNG)不足によって市場価格が一時的に200円/kWhを超える高値を記録しました。
電気代が高いと感じたらまずここをチェック!
ここまで、電気代が高くなる理由について解説してきましたが、実際に電気代が高いと感じた場合、どのような対応をすればよいのでしょうか。
電気代が高いと感じた際は、以下のポイントをチェックしてみましょう。
- 電気代の内訳を確認する
- 家電の使用状況を確認する
- 漏電していないか確認する
- 契約しているプランを確認する
ここでは、それぞれのポイントについて解説します。
電気代の内訳を確認する
電気代が高いと感じたら、まずは請求明細をチェックし、前月や前年の同月と比較してみましょう。使用量だけでなく、電力量料金単価や燃料費調整額などの内訳も確認することで、どの部分で料金が増えているかが分かります。
過去の明細と以下の項目を比較しましょう。
- 電気使用量
- 燃料費調整額
- 市場連動型の場合、電力量料金単価
家電の使用状況を確認する
使用量が増えている場合、家電の使用状況を確認することが重要です。例えば、「エアコンの使用時間や設定温度が変わっているか」「消費電力の大きな家電を長時間使用していないか」「使用頻度の多い家電が古くなっていないか」「待機電力が多い家電を増やしていないか」といった点を確認しましょう。
消費電力の大きな家電は、少しの使用時間でも電気代に影響します。また、電源を切っていても待機電力で電気代がかかるため、家電の使用方法を見直すだけでなく、待機電力の削減にも気を付けることが大切です。
漏電していないか確認する
漏電は火災のリスクを高めるため、危険な状態です。長期間にわたって異常に高い電気代が続いている場合は漏電の可能性があります。また、漏電ブレーカーが頻繁に落ちる場合も、漏電のサインです。
漏電の確認方法は、以下の通りです。
-
- 主幹ブレーカーをオンにし、分岐ブレーカーをオフにする
- 漏電ブレーカーをオンにする
- 分岐ブレーカーを1つずつオンにしていく
分岐ブレーカーを順にオンにしていくと、ブレーカーが落ちた箇所に漏電があることが分かります。漏電箇所を特定したら、該当の分岐ブレーカーをオフにして家電のコードやコンセントを確認し、漏電箇所を探しましょう。
契約しているプランを確認する
電気代が上がっている理由が使用量の増加でなければ、燃料費調整額の上昇や市場価格の上昇が影響している可能性があります。市場連動型のプランを契約していて、市場価格の影響が大きい場合は、固定単価型のプランへの変更によって電気料金の急激な変化を避けられる可能性があります。
また、契約中の電力プランが自分の生活スタイルに合っているかどうかも確認してみましょう。
電力会社によっては、次のようなプランがあります。
- 深夜だけ電気代が安くなるプラン
- 深夜と休日の電気代が安くなるプラン
- 使用量に応じた定額プラン
自分の使用時間帯に合わせてプランを選ぶことが大切です。また、契約しているアンペア数が、家庭の電気使用量と合っているかもチェックしましょう。契約しているアンペア数に対して、実際の使用量が少ない場合は、契約アンペア数を変更することで節約できることがあります。
電気代が高いと言えるのはいくらから?
電気代が高いと感じる基準は人それぞれですが、世帯人数や年齢によって平均的な電気代は異なります。政府統計の「家計調査」を参考に、電気代の平均額を確認してみましょう。
ここでは、一人暮らしの場合と2人以上の場合に分けて、電気代の月平均額についてご紹介します。
一人暮らしの場合
政府統計の「家計調査(家計収支編)2023年」のデータによると、単身世帯の電気料金の全国平均は下表の通りです。
| 単身世帯の電気代 | 電気代 |
|---|---|
| 全年齢の平均 | 6,726円 |
| 34歳以下 | 5,127円 |
| 35~59歳 | 6,576円 |
| 60歳以上 | 7,431円 |
| 65歳以上 | 7,389円 |
年齢別に電気代の平均額は異なるため、自分の電気代と該当する年代の平均額を比較することで、通常よりも高いかどうかを判断できます。
なお、全体平均と比べると、高齢世帯の方が電気代は高い傾向があります。これは、在宅時間が長いことが影響していると考えられます。
2人以上の場合
全国の2人以上の世帯の月平均電気代は、以下の通りです。
| 世帯の人数 | 電気代 |
|---|---|
| 全体平均 | 12,265円 |
| 2人世帯 | 10,940円 |
| 3人世帯 | 12,811円 |
| 4人世帯 | 13,532円 |
| 5人世帯 | 14,373円 |
| 6人世帯 | 18,941円 |
単身世帯の全年齢平均と比較すると、電気代の月平均額は世帯人数に応じて2倍から3倍となっています。世帯人数が増えるほど電気代が高くなり、2人世帯と6人世帯では8,000円ほどの差があります。
電気代が高いときの対処法
ここまで、電気代が高くなる要因や確認すべきポイントについて解説してきました。では、電気代が高いと感じた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
電気代を効果的に抑える方法は、以下の通りです。
- 家電の使い方を見直す
- 古い家電を買い換える
- 待機電力を減らす
- 契約プランを変更する
- 自家発電設備を利用する
ここでは、それぞれの対処法について詳しく見ていきましょう。
家電の使い方を見直す
電気代を下げるためには、まず電気の使用量を減らすことが大切です。消費電力の多い家電の使い方を工夫するだけでも効果はあります。
例えば、複数の部屋でエアコンを使用すると、その分電気代が高くなります。夏はエアコンを使用する部屋を決めたり、照明をこまめに消すようにしたり、節電を心がけると良いでしょう。
古い家電を買い換える
10年以上使用している家電は、最新のタイプよりも省エネ性能が低い傾向があり、電気代が高くなりやすいです。具体的には、エアコン・冷蔵庫・洗濯機などは、最新の製品と比べて消費電力に大きな差があります。
電気代を安くするためには、古くなった家電を買い替えることも一つの方法です。特に、電力を多く使用するエアコンや冷蔵庫、頻繁に使用する洗濯機は、買い替えによる効果が大きいです。
待機電力を減らす
待機電力とは、電源を切っていなくてもコンセントに差し込まれているだけで消費される電力のことです。リモコンやスイッチで簡単に起動できる家電は、待機電力が多く消費されることがあります。
待機電力は意外にも電気代を高くする要因となっており、以下の家電は特に待機電力を多く消費します。
- ガス温水器
- テレビ
- エアコン
- 電話機
- DVDやブルーレイのレコーダー
これらの家電を長時間使用しない場合は、主電源を切る、またはコンセントを抜くなどして、待機電力をできるだけ減らす習慣をつけることがポイントです。
電力プランを変更する
2016年の電力自由化以降、利用者は自由に電力会社を選べるようになりました。それまでは地域ごとに契約できる電力会社が決まっていましたが、今では自分に合った電力会社やプランを選択できます。
現在の電力プランが自分のライフスタイルに合っていないと感じたら、プラン変更を検討してみましょう。携帯電話や保険と同様に、適切なプランを選ばなければ、不必要に料金が高くなってしまいます。
電力プランを乗り換える際には、料金単価を比較し、シミュレーションして最適なプランを見つけることが大切です。電気使用量を確認した上で、各社のシミュレーションでおトクなプランを確認するほか、ライフスタイルに合った付帯サービスも確認しましょう。
例えば、出光興産では通常住宅向けに「idemitsuでんき Sプラン」およびオール電化住宅向けに「idemitsuでんき オール電化プラン」と2つの電力プランを用意しています。日々の電気代が安くなるほかにも、いつもの給油がおトクになるクルマ特割や、日常で使えるポイントが貯まるポイントプログラムも魅力的です。
まずは、現在の電気使用量と電気代を確認し、「idemitsuでんき」のシミュレーションで、電気代が安くなるかをチェックしてみましょう。
電力会社の変更・乗り換え時の注意点を紹介!失敗しない電力会社選びをしよう
自家発電設備を利用する
太陽光発電などの自家発電設備を利用することで、電気代を削減できます。太陽光発電は導入時のコストが大きいものの、発電した電気を自宅で使いきれなかった場合、余った電力を電力会社に買い取ってもらうことも可能です。また、災害時の備えとしてもメリットがあります。
さらに、太陽光発電とあわせて蓄電池を導入することで、夜間や雨天などでも蓄電池の電気を使用できます。
太陽光発電や蓄電池を設置するためには、設置する場所に制約がある場合があること、また導入時のコストも大きいことから、導入可否や設置する意味を事前に確認しておきましょう。
idemitsuでんきへの乗り換えで電気代をおトクに
電気代が高くなる主な要因として、電気使用量の増加や古い家電・消費電力の多い家電の使用、燃料費調整額や市場価格の上昇などが挙げられます。「電気代が高い」と感じた場合は、まず電気使用状況や契約プランを見直してみましょう。
idemitsuでんきなら、ウェブから簡単に申し込むことができ、事前のシミュレーションで節約額を確認できます。ライフスタイルにあわせたさまざまなプランを提供していますので、ぜひ一度チェックしてみてください。